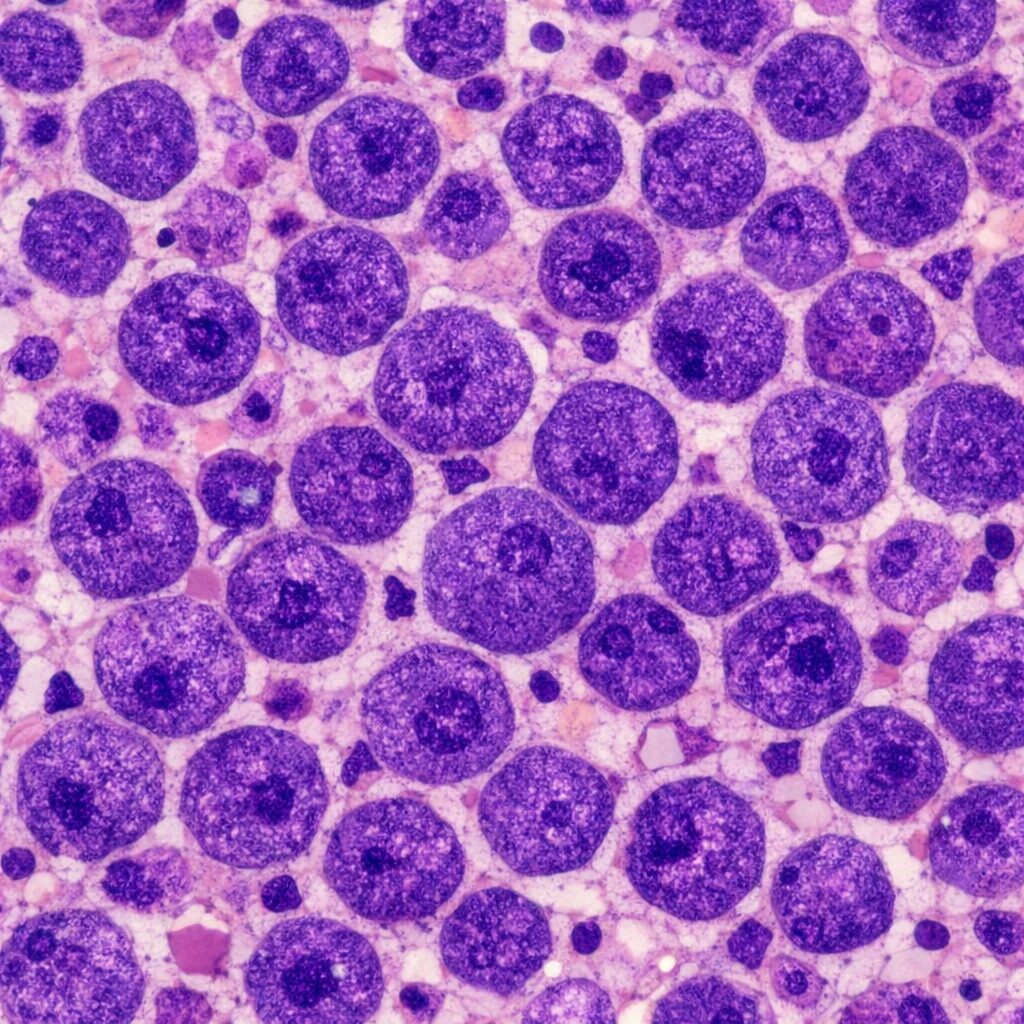1. 病気の概要
- 多発性骨髄腫(たはつせいこつずいしゅ)は、骨髄の中で抗体を作る「形質細胞」ががん化し、全身の骨髄で異常に増える病気です。
- 単発で発生する「髄外性形質細胞腫」や「孤立性骨形質細胞腫」とは異なり、全身性(多発性)に広がるのが特徴です。
- 犬では比較的まれですが、発生すると進行性・全身性であり、慢性的な貧血・出血・感染・骨痛などを引き起こします。
- 高齢犬(平均10歳前後)での発症が多く、特に大型犬での報告がやや多めです。
2. 症状
多発性骨髄腫は「どこの骨髄で増えているか」によって症状が多彩です。代表的なものは以下の通りです。
- 元気がない、食欲がない、体重減少
- 骨の痛みや跛行(びっこ)
→ 骨がもろくなり、**病的骨折(ちょっとしたことで折れる)**が起こることもあります。 - 貧血や血小板減少による出血傾向(鼻出血、皮下出血など)
- 血液の粘度上昇による神経症状
→ ふらつき、失明、けいれんなど - 腎臓障害(尿が濃くならない、BUN・クレアチニン上昇)
→ 腫瘍細胞が作る異常な免疫グロブリンが腎臓に沈着するため - 感染症の再発・難治化
→ 正常な免疫細胞が減少するため、皮膚炎や肺炎が続くことも
3. 診断方法
診断は「複数の証拠を組み合わせて」行います。
代表的な診断基準は以下の4項目のうち2つ以上を満たすこと:
| 検査項目 | 説明 |
|---|---|
| 骨髄検査 | 骨髄中に形質細胞が異常に増加(通常30%以上) |
| 血清・尿検査 | 単クローン性ガンマグロブリン(M蛋白)が確認される(免疫電気泳動) |
| 骨X線 | 骨に「打ち抜き様(パンチアウト)」の溶解性病変が複数 |
| 尿中Bence-Jones蛋白 | 腫瘍性免疫グロブリンの軽鎖成分が尿中に排出 |
追加で:
- 血液検査(貧血、蛋白濃度、カルシウム濃度)
- 尿検査(腎障害の程度)
- レントゲン・CT(骨破壊・転移評価)
- 骨髄穿刺による細胞診/病理
4. 治療方法
(1)化学療法
- 主体はメルファラン(アルケラン®)+プレドニゾロンの併用療法。
- 反応率は高く、約70〜80%の犬で臨床的寛解(症状改善)が得られるとされています。
- 初期は連日内服、安定期に入れば間欠投与に変更します。
- 副作用(骨髄抑制・胃腸障害など)は定期的な血液検査でモニタリング。
(2)支持療法
- 輸液:脱水・腎障害に対して
- 鎮痛薬:骨痛対策(NSAIDsやオピオイド)
- 抗生剤:二次感染予防
- 輸血:重度貧血時
(3)放射線治療
- 限局的な骨病変による痛みや脊椎圧迫などがある場合に、緩和目的で使用します。
5. 予後
- 初期治療に良好に反応すれば、平均生存期間は12〜18か月程度。
- 一方、治療抵抗性や再発時には予後は短縮(数か月〜半年程度)。
- 腎障害の有無が重要な予後因子で、腎臓に沈着がある場合は短命化します。
- 完治は困難ですが、症状を抑えながら生活の質を維持することが可能な腫瘍です。
6. 治療後フォロー
- 1〜2週ごとに血液検査(初期)、安定後は月1回程度でモニタリング。
- 定期的な骨レントゲン/尿検査で再燃や合併症の確認。
- 家庭では以下をチェック:
- 食欲・元気の変化
- 排尿量(腎障害のサイン)
- 骨の痛みや歩き方の異常
- 出血傾向
7. よくある質問(Q&A)
Q1:治りますか?
A1:完治は難しい病気です。ただし、治療に反応することが多く、1年以上安定した生活が送れるケースもあります。
Q2:他の臓器に転移しますか?
A2:骨髄系の病気なので「転移」というより、全身の骨髄に広がると考えます。
Q3:治療費はどのくらいかかりますか?
A3:初期検査〜治療導入で10〜20万円前後、以後は月2〜5万円程度の継続管理が一般的です。
Q4:痛みは強いですか?
A4:骨に病変がある場合は痛みが出やすいですが、鎮痛薬や放射線治療でコントロール可能です。
Q5:うつる病気ですか?
A5:いいえ、感染性ではありません。ほかの犬や人にうつることはありません。
8. 飼い主様へのメッセージ
- 多発性骨髄腫は「完治は難しいが、コントロールできるがん」です。
- 適切な化学療法により、痛みを軽減し、生活の質を維持できる期間を延ばすことが可能です。
- 定期的な検査と服薬が必要ですが、犬自身は治療を受けながら元気に過ごすことが多いです。
- 私たちは、「がんと付き合いながら穏やかに暮らす」ための治療を一緒に考えます。